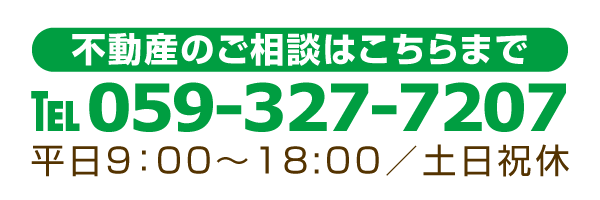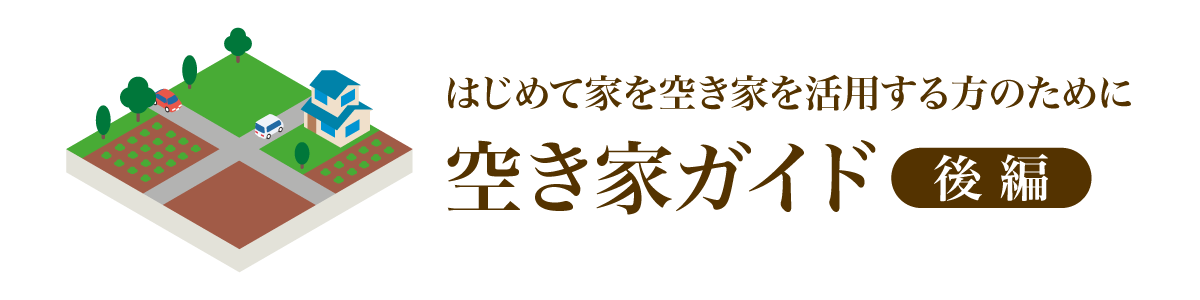空き家を活用する方法
空き家活用の基礎知識
空き家を貸す
賃貸借契約
最も単純な空き家活用の一つに、賃貸借契約を結んで空き家を貸すと言う方法があります。
不動産を貸すのは、借り手の生活にも大きく影響する重要な契約です。契約後に争わないためにも。慎重に考えて契約を行いましょう。不動産会社を通すことで、様々なアドバイスを受けたり、日々の管理などを代行してもらうことも出来ます。
賃貸借契約の種類
| 普通借家契約 | 定期借家契約 |
|---|---|
|
|
普通借家契約は一般的に2年ごとの更新で、原則貸主に正当な理由がないと更新の拒絶が出来ません。どうしても明け渡しを要求したい場合、金銭で保証するのが一般的です。
それに対し、定期借家契約はあらかじめ期間を限定した契約であるため、満了時点で確実に明け渡しを受けることが出来ます。定期借家契約には3つの借地権を設定出来ます。
| 一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
|---|---|---|---|
| 契約年数 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
| 主な用途 | 住宅 | コンビニなど | アパート・店舗など |
| 返還の方法 | 貸主が他当て物を取り壊してから更地にして返還する | 借主が建物を買い取る | |
駐車場として貸す場合は制限がない
上記の通り、借主は法律で保護されているため、契約解除をしてもらうためには、6ヶ月前通知や正当な理由が必要です。
しかし、駐車場として貸した場合の賃借権は、借地権ではないため借地借家法の適用外となり、貸主から一方的に契約解除を実行する契約も可能となります。
賃貸に向く物件・向かない物件
賃貸活用の選択肢
空き家は人が住んでいれば、荒れる心配もない上、家賃収入も見込まれ、固定資産税の支払いも吸収出来ます。
しかし、どんな物件でも貸し出せるわけではないため。賃貸に向いている物件かどうかを考える必要があります。
| 賃貸に向いてる物件 | 賃貸に向いていない物件 | |
|---|---|---|
| 戸建て |
|
|
| マンション |
|
|
自分で使用する
自己使用の選択とリスク
売却も賃貸もせずに、自分や家族で使用するのも一つの選択肢です。
セカンドハウスなどにして拠点を増やすことが出来る反面、所有し続けることによる税金や維持管理費の負担があるので注意が必要です。

自宅として住む
今の住まいを売却した資金で、地方の実家にリフォームして移住するUターンです。
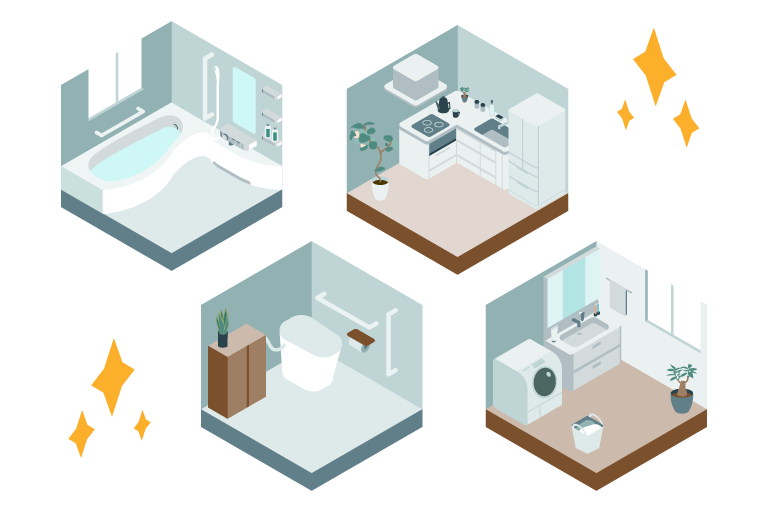
別荘として活用する
休日や週末に使うセカンドハウスとして活用します。

仕事部屋にする
リモートワークをしている方や事業主などの方は仕事部屋として活用出来ます。
再び空き家になるリスクも考える
- 維持管理がだんだん面倒になる
- 固定資産税の負担を感じる
- 価値が下がって売却も賃貸も出来なくなる
相続した実家をご自身で使うのは決して悪いことではありませんが、思ったほど活用することなく放置してしまうと、管理されない空き家と同じ状態になることが多分にあります。
空き家は定期的な通風や通水が必要です。とりあえず実家を残すと言う判断を行った場合でも、空き家は永遠に持つものではありません。売却や活用方法の出口を考えておくことも重要です。
売れない・貸せない不動産の選択肢
空き家バンクと地域貢献
不動産とは言え、そのすべてが売却・賃貸・自己使用に適しているわけではありません。しかし市場価値が低いからと言って、空き家・空き地を放置するわけにも行きません。自治体が行っている空き家バンクを利用したり、社会福祉に役立ててもらったり、最後は国に引き取ってもらうなどの方法もあります。
●空き家バンクの登録
市場価値がない家でも市区町村が創設している空き家バンクに登録することで、住む人が見つかる可能性があります。
国交省が選定している全国版の登録サイトもあります。
地域の公共施設として無償提供
土地を無償で提供する代わりに、地域の公共施設として使ってもらえる可能性のある自治体もあります。
社会福祉施設として活用
デイサービスやグループホーム、こども食堂など、高齢者や障がい者の施設が不足している実態に対し、自治体や社会福祉協議会を通じて空き家を活用を補助してもらえる場合があります。
自治体への寄付
市場価値のない空き家は自治体にとっても負担になるだけで、寄付のハードルが高い自治体もあります。
ただし、歴史的に価値の高い建物や、避難場所に適している広い土地などであれば、自治体だからこそ必要とされる可能性はあります。
相続土地国庫帰属制度
取引要件を満たせば、相続した土地を国が引き取る制度があります。審査手数料を支払い、要件を満たせば概ね20万円程度の負担金で、制度を利用することが出来ます。
有料引取サービスは注意
最終手段として、有料で業者に引き取ってもらうサービスがあります。しかし詐欺に利用される可能性もあり、宅建免許を確認するなどの注意が必要です。