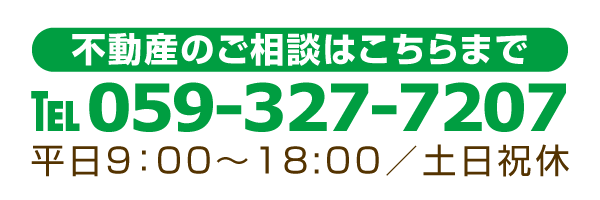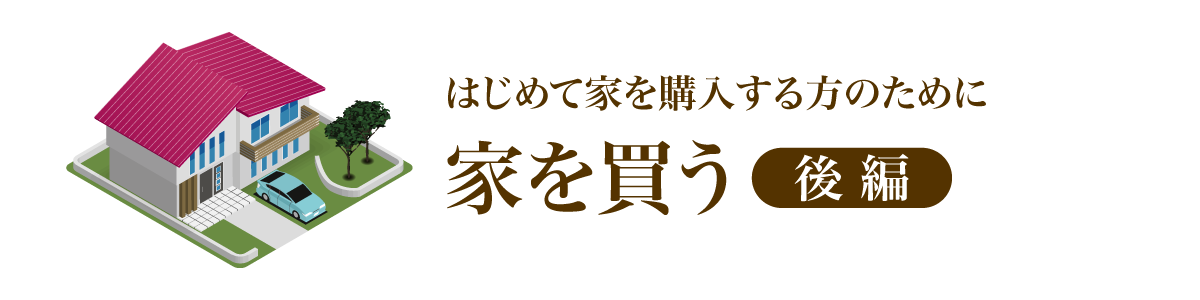購入するためのパートナー探し
不動産会社の選び方
マイホームを探す
物件と不動産会社探し
希望条件整理と資金計画を立てたら、次は物件と不動産会社探しになります。
情報収集の一般的な方法と注意点を押さえていきます。
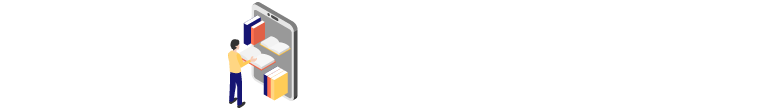
|

|
|---|---|
|
住宅情報サイトでは様々な物件が紹介されており、条件を絞り込んで検索することも出来ます。 不動産会社もネットでの情報発信に力を入れている他、新聞・折込チラシ・投函チラシ・住宅雑誌などのメディアからも情報を得られます。 |
ダイトー地所のような地域の情報に精通した地元の不動産会社の店舗に行くと、住まい探しのサポートをしてもらえます。 まだ売りに出す前の物件を教えてもらえる他、生活の利便性・環境など地域に関することが聞けます。 |
新築住宅の広告の注意点
新築分譲広告には、目に止まりやすく興味を抱かせる夢と希望のキャッチコピーやイメージ写真が並んでいます。
しかし、広告の見出しだけでは大まかな特徴しか分からず、買主にとって本当に必要な細かい情報は小さな文字の中にあります。
気になる物件は小さな文字を注意深く読んでいきましょう。
不動産に格安物件はない
格安物件は不動産会社が購入して相場並みの価格で再販売されます。
消費者が目にする不動産情報の中に格安物件・掘り出し物物件はありません。
安い物件には理由=瑕疵(欠陥)があり、おとり物件であるケースもあり、興味本位でこのような物件を見学に行ったりすると危険です。
物件選びで注意すべきこと
購入後に毎日そこに帰ることになる住宅購入において、実際にそこに住んだつもりで日常生活を想像しながら行動してみることが重要です。
交通・買い物・学校・病院などの周辺環境や、日当たり・眺めなども自分の目と耳で確認することをオススメします。
新築住宅の見学
新築の場合、モデルルームの見学で完成状態を確認することが出来ますが、モデルルームはオプションの内装材や設備を使用しているケースが多いです。
そのため、基本仕様との違いを確認することが重要です。
中古住宅の見学
売主が立ち会う場合、節度ある態度で売主を不愉快にさせないように注意しましょう。また、写真の撮影は事前に売主の承諾を得ておく必要があります。売主は物件の状態や生活の利便性などの情報をたくさん知っていますので、失礼のない範囲で確認しましょう。
また、中古マンションの場合、駐輪場・ゴミ置き場などの共用部分の管理状態を確認しておいた方がよいでしょう。
| 敷地 | 地形・境界標の有無・地盤の状況・道路や隣接地との高低差・電柱の位置など |
|---|---|
| 道路 | 種類(私道でないか)・幅員・舗装の状態など |
| 工作物 | 門・塀などの状況や安全性など |
| 擁壁 | 構造(RC造/石積みなど)・高さ・ひび割れ・水抜きの有無など |
| 車庫 | 幅×奥行・カーポートの有無・入出庫時の使い勝手など |
| 建物外部 | 築年数・痛み具合・外壁塗装の状況・基礎などのひび割れ・屋根瓦の状況など |
| 建物内部 | 間取り・使い勝手・劣化状況・雨漏り・シミ・ひび割れ・建具の開閉状況など |
| 付帯設備 | 設備の状態・故障履歴など |
| その他 | 越境物(樹木など)・隣接地建物の種類・方位・ゴミ出しルール・自治会ルール・近隣トラブルの有無など |
不動産会社に仲介を依頼する
媒介契約
購入希望者から仲介の依頼を受けた媒介業者(仲介業者)は、媒介契約を行った後、売買契約の成立に向けて尽力します。
また、契約成立後は買主の義務履行のためにアドバイスや補助業務を行い、安全に取引が成立するように進行させます。
媒介会社がしてくれること
| 契約前 | 契約後 |
|---|---|
|
|
売買代金が400万円超の仲介料の簡易計算式

マイホームの契約・購入
購入申込・住宅ローン・売買契約
売買契約前に行うこと
購入申込・住宅ローン審査
物件が決まったら購入手続きに移ります。
売主と買主の利害は反しますので、契約条件の調整が必要になります。媒介業者は双方の契約条件を調整し、売買契約書(案)を作成します。
新築分譲住宅など、売主が不動産会社の場合はあらかじめ売買契約書(案)が作成しており、原則その内容で契約することになります。
購入申込から売買契約までの流れ
- 案内
-
購入申込・条件交渉
売買代金 契約代金 支払い方法 手付の額・中間金支払いなど 売買方式 (中古戸建て住宅の場合)実測売買or公簿売買 引渡条件 付帯設備・庭石・植木等の範囲 融資利用 融資利用特約の内容 瑕疵担保責任 瑕疵担保責任特約の内容 その他 手付解除期日・税の精算基準日・買換え特約等・その他条件 -
- 住宅ローン事前審査
-
重要事項説明 諸検査依頼 リフォーム等の内覧・計画確認
-
-
- 条件合意
- ローン審査承諾
-
諸検査 売買確認
-
- 売買契約
重要事項説明を受ける
重要事項説明
住宅購入をする上で知っておくべき必要な情報があります。それらを知らないことで、思わぬ損失や不利益を被ることがあります。
宅地建物取引業法では、そのような事態が起こらぬように買主の代わりに必要情報を調査し、重要事項説明書を作成・説明することが義務付けられています。
売主・買主の条件がまとめられた重要事項説明は、契約を結ぶかどうかの判断で最も重要なものとなります。
疑問点や知りたいことがあれば、しっかりとここで確認しておきましょう。
重要事項説明のポイント
●不動産
取引対象となる物件の詳細が記載されています。
原則、登記簿謄本の表題部がそのまま記載され、売買対象物が登記簿に記録された物件の一部である場合や、現状が登記と異なる場合があります。
●売主
登記簿に記載された登記名義人が売主であることが通常ですが、相続登記が未了の場合など、真の所有者が登記名義人でないこともあります。
説明内容をしっかりと確認することを心がけましょう。
●法令上の制限
自分の土地であっても、法律で制限を受けている場合は自由に利用できるわけではありません。
建物の規模・形状・用途などが制限されている場合、将来希望する建物に建て替え可能かどうかをしっかりと確認します。
●生活関連施設
現在使用可能な施設、または将来に渡り整備が予定されている施設について説明を受けます。
場合によってはそのまま使い続けることが出来ないケースや、負担金が生じる場合もあります。
●その他
宅建業法により、重要事項として説明が義務付けられていること以外にも、越境物の有無・交通の利便性・近隣の住環境などについても確認が必要です。
これらは重要事項説明書の最後にある「その他」の欄で説明されます。
売買契約を結ぶ時の注意点
売買契約
売買契約は書面がなくても、当事者間の「契約する意思の合致」(諾成契約)で成立しますが、約束事は書面にしておかないと、後々トラブルの原因となります。
宅建業法では、諾成契約のトラブル防止のために、契約内容を記載した書面「37条書面」を双方に交付することが義務付けられています。
通常は売買契約書がこれを兼ねています。
売買契約のポイント
●約束事は必ず書面にする
売主・買主が約束したことは小さな事であっても契約書に特約として記載しておくことがトラブル防止につながります。
①約束事項 ②年月日 ③約束した人間の署名・捺印 を記した書面を作成しておきましょう。
●契約内容を確認する
契約書にサインする前に、もう一度契約内容の確認をしましょう。通常は仲介業者が契約書を読み上げて、双方の読み合わせにより最終確認をします。
契約当日に新たな契約条件や変更をすることのないよう、早い段階で契約内容を確認しておくことが必要です。
●契約を締結する
契約書に押す印鑑は認印でも問題ありませんが、通常は実印を押印しますので、仲介業者に確認しておきましょう。
契約書をはじめ、様々な書類への押印は、書類の内容を確認して必ず自分で行います。
印鑑を預けることは大変危険ですので、絶対にしてはいけません。
●売買代金の支払い方法
支払い方法は契約交渉の際に契約交渉の際に決まっていますが、一般的には売買契約時に手付金を支払い、残金は一括で引き渡しと同時に支払います。
住宅ローンを利用しており、融資実行が引き渡し後になる時は、売主が融資金を直接受け取る「代理受領」手続きや「つなぎ融資」を受けることが必要になることがあります。
●手付金はいくら払うのか
金額に決まりはありませんが、売買代金の5〜10%が一般的です。
契約後にすること
残金決済と引き渡し
買主が売買代金の全額を支払うことを決済と言い、物件の引き渡しと同時に行われます。
引き渡しは①買主への所有権移転に必要な登記書類の引き渡し ②建物の鍵の引き渡し を行い、物件引き渡し確認書を作成して交付するのが一般的です。
購入後にかかる税金
住宅取得にかかる税金は、売買契約締結時の印紙税の他、建物の引き渡し時に必要な「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」などに必要な印紙税が必要となります。また、不動産取得にかかる不動産取得税を納めなければなりません。
様々な減税措置があり、厳格な要件を満たすと、融資を利用した場合の「住宅ローン控除」や、所得税の特別控除など、多種多様な減税措置を受けることが出来ます。
不動産会社も税金の大まかな知識は有していますが、税金に関することは税理士や税務署の相談窓口で確認するようにしましょう。
| 住宅ローン控除 | 年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定の金額を所得税額から控除 |
|---|---|
| 特定の増改築等にかかる住宅ローン控除の特例 | 住宅のバリアフリー・省エネ・他世帯同居回収工事等 |
| 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 | |
| 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 | 一定のバリアフリー・省エネ・多世帯同居改修工事をした場合、耐久性向上改修工事をした場合 |
| 認定住宅の新築等をした場合の所得税の特別税額控除 | 新築または建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得 |
| 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 | 父母・祖父母などからの住宅取得等資金の贈与における非課税措置 |
| 相続税・贈与税の一体化措置(相続時精算課税制度) | |
| 贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与) | 夫婦間の居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与 |